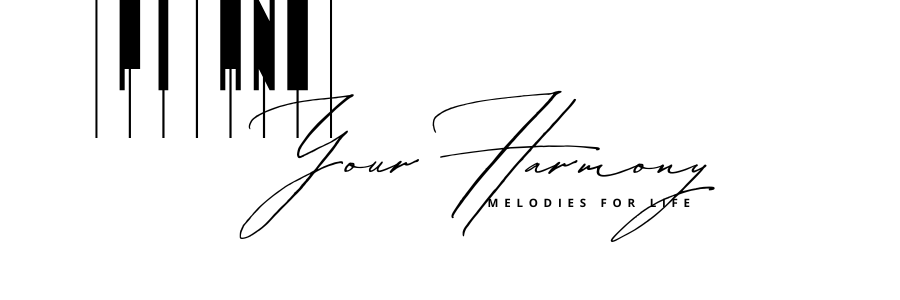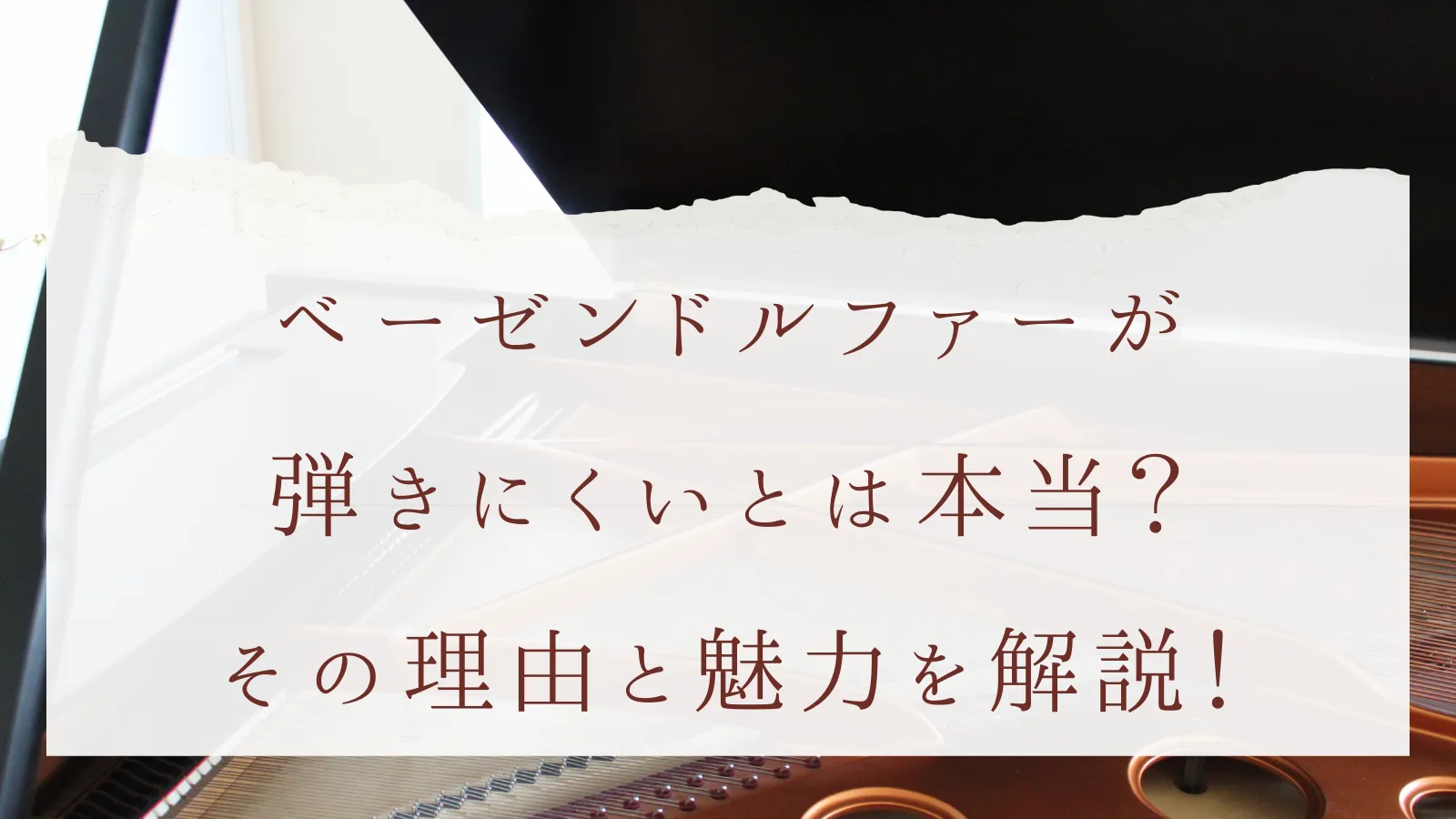ベーゼンドルファーは、その特徴的な音色と構造により、愛用するピアニストが多い一方で「鍵盤が重い」と感じる声もあります。
リストも称賛したこのピアノは、調整状態やタッチの慣れによって印象が変わることがあるため、誤解されやすい側面もあるようです。
この記事では、ベーゼンドルファーに合う曲、価格、日本に何台あるかといった希少性、ヤマハとの関係など、さまざまな視点からその魅力と実情を解説します。
こんな方におすすめ
- ベーゼンドルファーの演奏感や特徴が気になっている
- 購入を検討していて情報を集めている
- 他のピアノとの違いを知りたい
- 演奏性の悩みやタッチの違和感に納得したい
ベーゼンドルファーが弾きにくいといわれる理由と魅力
この項のポイント
-
鍵盤重いと感じる原因とその実態
-
ベーゼンドルファーの特徴とは何か
-
調整状態による弾きにくさの差
-
スタインウェイとのタッチ比較
-
ベーゼンドルファーに合う曲と演奏傾向
鍵盤重いと感じる原因とその実態

鍵盤が重く感じられる理由のひとつに、アクションの構造と調整状態があります。
ベーゼンドルファーは、表現の幅を広げるために高い応答性を持たせた設計がされていますが、それが一部の人には「重い」と感じられることもあるようです。
とはいえ、全ての個体が同じ重さというわけではありません。
ピアノの鍵盤の重さは実は個体差が大きく、例えば購入から10年ほど経ったピアノでは、高音部が60g、中音部で65g、低音部では70g近くになっていたという事例もあります。
このくらいになると、確かに「ずっしりと重い」と感じるのも無理はありません。
ただし、この重さは「もともとそういう仕様」ではなく、内部の摩耗やセンターピンの劣化が影響していることが多いです。
センターピンを交換し、適切な調整を施せば、一般的なグランドピアノと同じ50g前後に落ち着くこともあります。
実際、スタインウェイの出荷基準も約47〜52g程度で、きちんとメンテナンスされたベーゼンドルファーもそれに近い数値になることが多いです。
このように、鍵盤が重いと感じる場合は、必ずしもベーゼンドルファーの設計が原因とは限らないということを知っておくと安心です。
ベーゼンドルファーの特徴とは何か

ベーゼンドルファーには、他のピアノではなかなか味わえない独自の個性があります。最も代表的なのが「ウィンナートーン」と呼ばれる音の質感です。
オーケストラのような厚みと、柔らかくてあたたかい音色が特徴的で、特にピアニッシモの美しさには定評があります。
音を出す仕組みにも工夫があります。一般的なピアノは響板のみが共鳴しますが、ベーゼンドルファーはケース全体が共鳴体として機能する「鳴る箱構造」を採用しており、まるで楽器全体が歌っているような印象を与えてくれます。
また、鍵盤やアクション部分には、演奏者の微妙な力加減に応える繊細な設計がされています。
表面素材「タラン」は象牙の質感を再現し、滑りにくく心地よいタッチを実現しています。弾き心地が柔らかく、感情表現を豊かに伝えられるのもこの素材のおかげです。
このような細部へのこだわりと手作業による製作によって、ベーゼンドルファーは「ただの高級ピアノ」ではなく、芸術作品のような存在になっているのです。
調整状態による弾きにくさの差

どんなに高品質なピアノであっても、調整が行き届いていないと演奏性は大きく損なわれてしまいます。ベーゼンドルファーも例外ではありません。
特に敏感な構造を持っている分、わずかな不調でも弾きにくさを感じやすい傾向があります。
例えば、鍵盤の土台となる「鍵盤筬(けんばんおさ)」が浮いていると、打鍵時に「コトコト」という異音が出たり、打感がフワフワして安定しなかったりすることがあります。
また、内部のベディングスクリューが緩んでいる場合も、アクション全体の反応が鈍くなってしまう原因になります。
これらの問題は決してベーゼンドルファー固有の欠点ではなく、定期的なメンテナンスで十分に対応可能です。専門の技術者による整備を受けることで、本来のスムーズな演奏感がよみがえるケースも多くあります。
つまり「ベーゼンドルファーが弾きにくい」と感じる人がいたとしても、それが本当に設計上の問題なのか、それとも調整不足なのかを見極めることが大切です。
きちんと調整された状態で弾けば、その印象は大きく変わるはずです。
スタインウェイとのタッチ比較

スタインウェイとベーゼンドルファーを弾き比べたとき、タッチの違いに驚く人は少なくありません。どちらも世界的な名器ですが、アクションの感触や音の立ち上がり方には明確な違いがあります。
スタインウェイの鍵盤は、反応が早く、比較的軽いと感じる方が多いようです。アタックがはっきりしていて、少ない力でも音が立ち上がりやすく、ダイナミックな演奏に向いています。
コンサートホールでの使用頻度が高いこともあり、「これがスタンダード」と思っている方にとっては、弾きやすく感じられるかもしれません。
一方で、ベーゼンドルファーはやや深く沈み込むようなタッチで、鍵盤を押す力のコントロールがより求められます。これは弾きにくいというよりも、音に厚みや深さを出すための設計上の特徴といえます。
演奏者が音をしっかり「掴む」ような感覚で弾く必要があるため、最初は違和感を覚えるかもしれませんが、慣れてくると繊細なニュアンスを表現しやすくなります。
このように、それぞれのピアノが持つ設計思想に違いがあるからこそ、演奏スタイルや好みによって「合う・合わない」が分かれるのです。
ベーゼンドルファーに合う曲と演奏傾向

ベーゼンドルファーの持ち味は、豊かな共鳴と繊細なピアニッシモです。そのため、細やかな音色の変化や、歌うようなフレージングが求められる曲との相性がとても良いと言われています。
ウィーン生まれのピアノらしく、モーツァルトやシューベルト、ベートーヴェンといったウィーン古典派の作品には特に適しています。
やわらかく澄んだ音色が、これらの作曲家が意図した「自然な歌いまわし」を美しく表現してくれます。
また、ドビュッシーやフォーレ、メシアンといった印象派の楽曲とも好相性です。音の持続時間が長く、倍音が豊かなので、ペダルを使った空間的な響きを活かしたい場合にもぴったりです。
一方で、はっきりとしたリズムやアタックを重視する曲では、最初は演奏に戸惑うことがあるかもしれません。
ベーゼンドルファーは、やや穏やかな立ち上がり方をするため、パーカッシブなタッチに慣れた方には少し遠回りに感じることもあります。
それでも、音の奥行きや表現の自由度を追求する方には、ベーゼンドルファーのサウンドは唯一無二の魅力になります。特に叙情性の高い作品を演奏する際には、その本領を発揮してくれるピアノです。
ベーゼンドルファー弾きにくいは本当か?
この項のポイント
-
愛用ピアニストの選択理由
-
リストが評価した頑丈さと音色
-
ヤマハとの関係と製造の違い
-
日本に何台ある?希少性の実情
-
モデルごとの価格と購入時の注意点
愛用ピアニストの選択理由

ベーゼンドルファーを選ぶピアニストには、ある共通点があります。それは、音色に対するこだわりと、表現力の幅を重視しているという点です。
このピアノは、繊細なピアニッシモから重厚なフォルテッシモまで、非常に広いダイナミクスに対応できるため、自分の音楽性を深く掘り下げたい演奏家に好まれています。
例えば、アンドラーシュ・シフ氏は、ウィーンのオペラシティでベーゼンドルファーを指名し、自身の演奏活動に活用しています。
また、日本人ピアニストでも久元祐子さんや加古隆さんなど、クラシックだけでなく多様なジャンルで活躍する方々が使用しています。
このことからも単に伝統的な楽器というだけでなく、現代の音楽表現にも十分に応えられるピアノであることがうかがえます。
さらに、オスカー・ピーターソンのようなジャズピアニストも愛用していたことから、音のふくらみやタッチの自由度が即興演奏にも合うことがわかります。
単なるブランドとしてではなく、「自分の音を自在に操りたい」と思う演奏家たちが、ベーゼンドルファーを手に取るのです。
リストが評価した頑丈さと音色
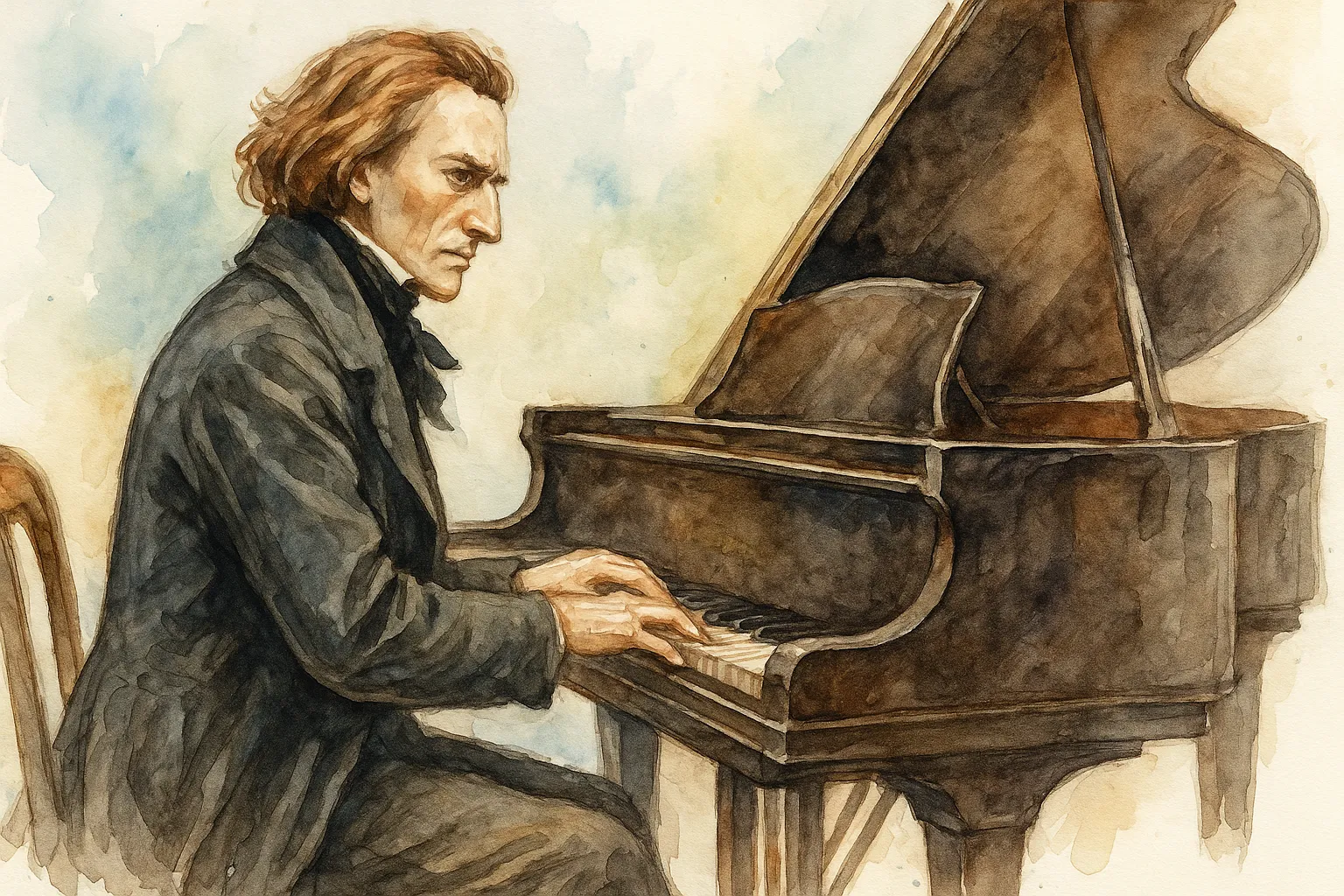
画像はイメージです
フランツ・リストとベーゼンドルファーの関係は、ブランドの歴史においても特別なものです。
演奏中にピアノを壊してしまうほどの強靭なタッチで知られていたリストですが、ベーゼンドルファーのピアノは彼の激しい演奏にも耐え抜いたという逸話があります。
この経験から、リストはベーゼンドルファーの耐久性と構造的な完成度を高く評価しました。そして、自身のコンサートでも使用するようになり、その評判が一気に世界中へ広がるきっかけとなりました。
ただ頑丈なだけでなく、音色の豊かさにも惹かれていたようです。ベーゼンドルファーの響きは、華やかでありながら深みがあり、フォルテでも耳に刺さらず、弱音ではしっとりと空間に広がっていきます。
リストの作品は、感情の起伏が大きく、急激なダイナミクスの変化や広い音域を要求されることが多いですが、こうした特性とベーゼンドルファーの音作りは非常に相性が良かったと考えられます。
このように、リストの実体験がベーゼンドルファーの品質を証明する大きな後押しとなり、楽器としての信頼性と芸術性の両方を世界に知らしめたのです。
ヤマハとの関係と製造の違い

ベーゼンドルファーは2008年にヤマハの子会社となりましたが、製造体制には大きな変化がないことをご存じでしょうか。
ヤマハが所有することで経営面では安定性が増しましたが、製造そのものは今でもオーストリアで行われています。
実際、ベーゼンドルファーは今も伝統的な手作業を大切にしており、職人たちが長い時間をかけて1台1台仕上げています。
使われる木材も、オーストリアやその周辺の厳選されたスプルース材が中心で、響きの美しさを生み出すために6年もの天然乾燥を経てから加工されます。
ヤマハは、マーケティングや販売面での支援はしているものの、音づくりや設計には関与していないとされています。
そのため、ヤマハ製のピアノとベーゼンドルファーでは、音の傾向や演奏感にははっきりとした違いがあります。ヤマハがクリアで明るい音を得意とする一方で、ベーゼンドルファーは温かみと包み込むような響きが特徴です。
このように、ヤマハとの関係は「経営のバックアップ」としての位置づけであり、音や製造の個性は守られたままというのが現状です。
日本に何台ある?希少性の実情

ベーゼンドルファーは、年間生産台数がわずか300台ほどに限られており、世界的に見ても非常に数の少ないピアノです。
これは、1台あたりにかかる製作期間が長く、また手作業で仕上げられる工程が多いためです。創業から約200年が経ちますが、これまでに製造された総台数はわずか5万台程度とも言われています。
日本国内で実際に流通している数について明確なデータはありませんが、その希少性は間違いなく高いです。
主要な正規販売店やショールームでも、常にすべてのモデルが揃っているわけではなく、試弾するにも予約が必要なことがほとんどです。
また、全国のヤマハミュージックジャパンの拠点や、専門店の限られたショールームでしか展示されていないことからも、その特別感が伝わってきます。
なかには、個人所有のモデルが演奏家の自宅スタジオに設置されているケースもありますが、一般家庭で目にする機会は多くありません。
こうした状況を見ると、ベーゼンドルファーはまさに「選ばれた人が持つピアノ」と言えるかもしれません。
モデルごとの価格と購入時の注意点

ベーゼンドルファーの価格帯は、一般的なピアノと比べてかなり高めです。たとえば、最上級モデルである「インペリアル290」は約4700万円、セミコンサートサイズの「280VC」でも約3700万円ほどします。
最小モデルである「155VC」でも2000万円前後とされており、アップライトタイプでも1000万円近くに達することがあります。
このような価格になる理由は、限られた素材、高度な職人技、そして長期にわたる製作工程にあります。さらに、拡張鍵盤(97鍵や92鍵)など独自の構造も加わり、コストはさらに上がります。
購入を検討する際に注意したいのは、「調整済みかどうか」と「設置環境」です。
ベーゼンドルファーは、響きに敏感な構造を持っているため、設置場所の広さや音の反響の仕方によっても印象が変わることがあります。防音対策や湿度管理もしっかり行う必要があります。
また、中古市場に出回る数が少ないため、気になるモデルがあったら早めに問い合わせるのがおすすめです。
新品であっても納品までに時間がかかることがあるので、タイミングを逃さないことが重要です。購入は一生の決断になる可能性が高いため、十分な試弾と相談の時間を取りましょう。
まとめ:ベーゼンドルファー弾きにくいは誤解されやすい特性だった
いかがでしたか?ベーゼンドルファー弾きにくいという声の多くは、調整状態や慣れによるものであることがわかりましたね。それでは最後に本記事のポイントをまとめます。
ポイント
-
-
鍵盤が重く感じるのはメンテナンス不足が原因であることが多い
-
経年劣化により鍵盤の重さが基準値を超えることがある
-
センターピンの交換などで適正な重さに戻せる
-
正常な調整状態では一般的なピアノとほぼ同じタッチになる
-
響板だけでなくケース全体が鳴る構造を採用している
-
豊かな倍音とサスティンを持つ「ウィンナートーン」が特徴
-
表面素材に「タラン」を用い、滑らかなタッチを実現している
-
調整が不十分だと打鍵の反応に違和感が出やすい
-
鍵盤筬の浮きやベディングスクリューの緩みで弾きにくくなる
-
ベーゼンドルファーは敏感な構造ゆえ調整の影響を受けやすい
-
スタインウェイよりも沈み込みが深く、タッチに慣れが必要
-
モーツァルトやドビュッシーなど叙情的な曲と相性が良い
-
オスカー・ピーターソンなどジャンルを超えて愛用されている
-
年間生産300台と非常に希少で、日本国内の流通数も限られている
-
価格は最小モデルでも2000万円前後と非常に高額である
-