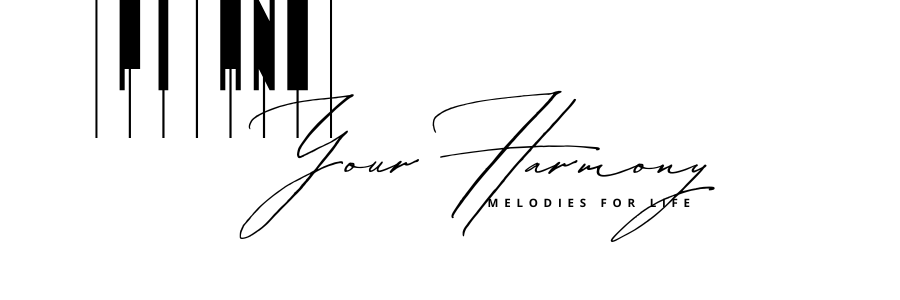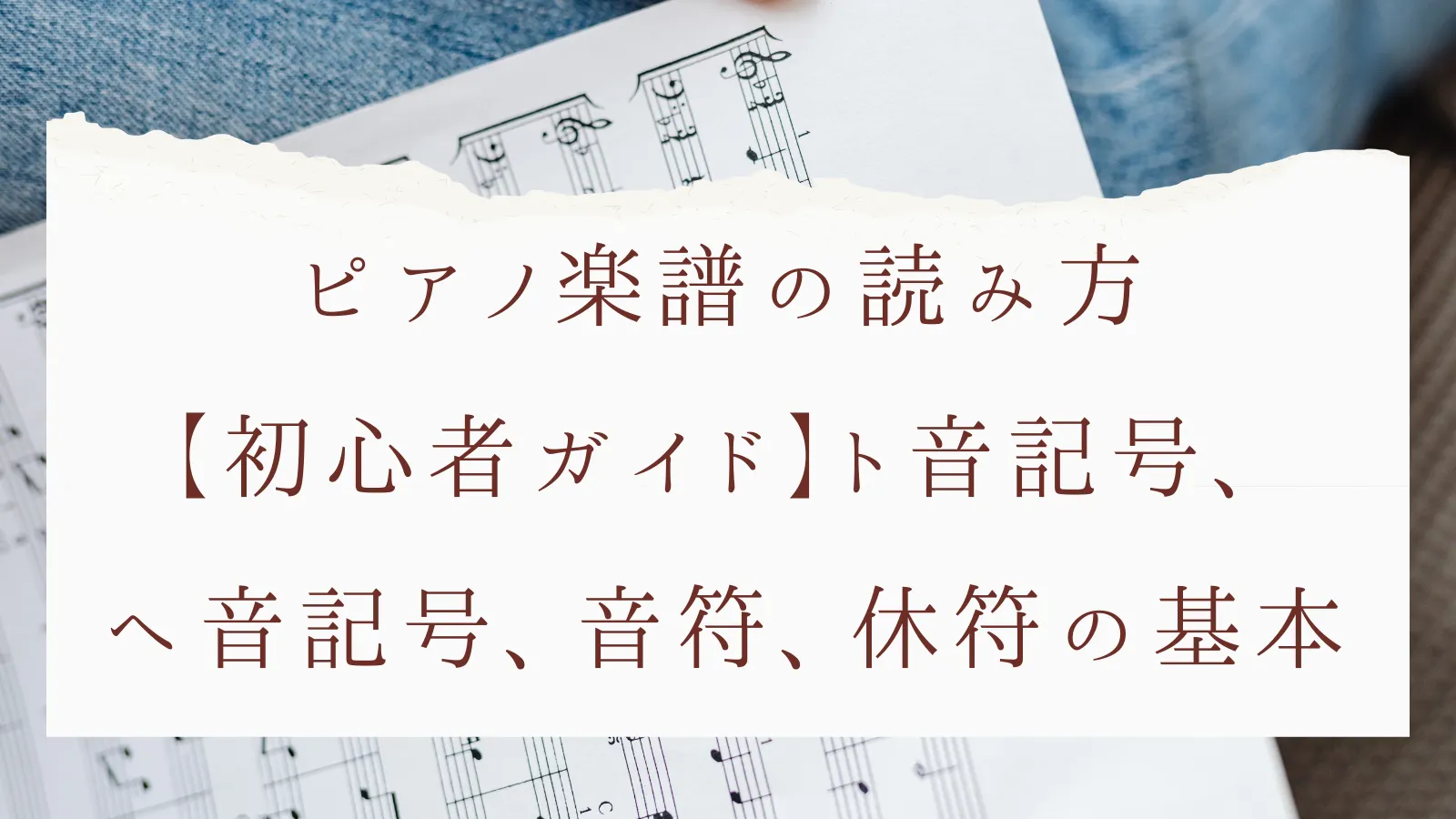「ピアノを弾いてみたいけれど、楽譜がまったく読めない」。
そう思って、一歩を踏み出せずにいませんか。
ピアノの楽譜は、一見すると複雑な記号の集まりに見えるかもしれません。
しかし、楽譜は「音楽の設計図」であり、一つひとつの記号には明確なルールがあります。
この記事では、ピアノ楽譜の読み方を知りたい初心者の方に向けて、楽譜を読むために必要な最低限の基本ルールをゼロから徹底的に解説します。
ト音記号やヘ音記号の違い、ピアノの音符の読み方、休符の長さまで、この記事を読み終える頃には、楽譜が「ただの記号」ではなく「音楽の言葉」として見えてくるはずです。
ピアノ楽譜の基本構成「五線譜」とは?
まず、ピアノの楽譜の土台となっている5本線について知りましょう。
楽譜は、基本的に「五線(ごせん)」と呼ばれる5本の平行な線の上に、「音符(おんぷ)」を置くことで作られています。
この線は下から「第1線」「第2線」「第3線」「第4線」「第5線」と数えます。
そして、線と線の間のスペースは「間(かん)」と呼ばれ、下から「第1間」「第2間」「第3間」「第4間」と数えます。
音符は、この「線の上」か「間」のどちらかに置かれ、その位置によって音の高さが決まります。
楽譜の読み方の「カギ」を握る!ト音記号とヘ音記号
五線譜の左端には、必ず「音部記号(おんぶきごう)」と呼ばれる記号が書かれています。
これは、五線譜上のどの位置がどの音の高さになるのかを示す、楽譜の読み方の「カギ」となる非常に重要な記号です。
ピアノでは主に2種類の記号を使います。
ト音記号(トおんきごう)とは?
ト音記号は、多くの人が「楽譜」と聞いてイメージする、最も一般的な記号です。
ピアノでは主に、メロディーラインとなる「右手」で弾く、比較的高い音域のパートを書き表すのに使われます。
この記号の書き始め(ぐるぐると巻き始める中心部分)が、五線譜の下から2番目の線(第2線)にあります。
この第2線が「ト」の音、つまり「ソ」の音であることを示しているため、「ト音記号」と呼ばれます。
ヘ音記号(ヘおんきごう)とは?
ヘ音記号は、ト音記号とは反対に、主に「左手」で弾く、低い音域のパート(伴奏など)を書き表すのに使われます。
この記号の書き始め(黒い丸の部分)は、五線譜の上から2番目の線(第4線)にあります。
この第4線が「ヘ」の音、つまり「ファ」の音であることを示しているため、「ヘ音記号」と呼ばれます。
なぜ2種類も必要なのか?
ピアノはバイオリンや人間の声と比べて、出せる音の範囲(音域)が非常に広い楽器です。
もしト音記号だけでピアノのすべての音を書き表そうとすると、五線譜から大きくはみ出してしまい、何本も線(加線)を足さなければならず、非常に読みにくくなります。
そこで、高い音は「ト音記号」、低い音は「ヘ音記号」と役割分担をすることで、楽譜をスッキリと読みやすくしているのです。
ピアノの楽譜では、このト音記号の五線譜とヘ音記号の五線譜をセットにした「大譜表(だいふひょう)」が使われるのが一般的です。
ピアノの「ドレミ」はどこ?音の高さ(音程)の読み方
ト音記号とヘ音記号の役割がわかったら、いよいよピアノの音符の読み方、具体的には「ドレミ」の位置を覚えていきましょう。
音符は、五線譜の中で「上」に行けば音が高くなり、「下」に行けば音が低くなります。
【ト音記号】「ド」の位置を覚える
ト音記号の楽譜を読むとき、基準となる「ド」は、五線譜のすぐ下(第1線の下)にあります。
この音符には、五線譜からはみ出しているため、専用の短い線「加線(かせん)」が引かれます。
この「ド」の位置さえ覚えてしまえば、あとは簡単です。
「ド」の次は「間」に「レ」、次は「第1線」に「ミ」、「第1間」に「ファ」…というように、「線→間→線→間」と順番に音が上がっていきます。
- ド:五線譜の下に加線
- レ:五線譜のすぐ下(第1線の下)の間
- ミ:第1線の上
- ファ:第1間
- ソ:第2線の上(ト音記号の基準の音)
- ラ:第2間
- シ:第3線の上
- ド:第3間
まずは、このト音記号の「ドレミファソラシド」の位置関係をしっかり覚えることが、ピアノ楽譜の読み方をマスターする第一歩です。
【ヘ音記号】「ド」の位置を覚える
次に、ヘ音記号の「ド」の位置です。
ヘ音記号の基準となる「ド」は、五線譜のすぐ上(第5線の上)にあります。
こちらもト音記号のドと同じように「加線」が引かれます。
そして、このヘ音記号の「ド」は、実は先ほど覚えたト音記号の「ド」と、ピアノの鍵盤でいうと「同じ音(真ん中のド)」なのです。
ヘ音記号では、この「ド」を基準に、音が下がっていきます。
- ド:五線譜の上に加線
- シ:第5線の上
- ラ:第4間
- ソ:第4線の上(ヘ音記号の基準の音)
- ファ:第3間
- ミ:第3線の上
- レ:第2間
- ド:第2線の上
このように、ピアノの大譜表は「真ん中のド」を中心に、高い音(右手)がト音記号で上に、低い音(左手)がヘ音記号で下に広がっていくイメージを持つと分かりやすいでしょう。
音の長さを決める!音符と休符の読み方
音の高さ(ドレミ)の読み方がわかったら、次は「音の長さ」です。
ピアノの音符の読み方では、音の高さと同時に、その音をどれくらいの長さで弾き続ける(または休む)のかを理解する必要があります。
基本となる「4分音符」をマスターしよう
初心者が音の長さを覚えるには、まず「4分音符(しぶおんぷ)」を基準にするのがおすすめです。
4分音符は、黒い丸に棒がついた形の音符です。
これは、手拍子を「タン」と1回打つ長さ、つまり「1拍(いっぱく)」分の長さを表します。
よく出る音符の種類と長さ
4分音符=1拍を基準にして、他の音符の長さを覚えていきましょう。
- 全音符(ぜんおんぷ):白い丸だけの音符。 4拍伸ばします(4分音符4つ分。「ターーーアン」)。
- 2分音符(にぶおんぷ):白い丸に棒がついた音符。 2拍伸ばします(4分音符2つ分。「ターン」)。
- 4分音符(しぶおんぷ):黒い丸に棒がついた音符。 1拍です(基準。「タン」)。
- 8分音符(はちぶおんぷ):黒い丸に棒と旗(はた)が1本ついた音符。 0.5拍(半拍)です(4分音符の半分の長さ。「タ」)。
- 16分音符(じゅうろくぶおんぷ):旗が2本ついた音符。 0.25拍です(4分音符の4分の1の長さ)。
これ以外にも、音符の右に小さな点「・」(付点:ふてん)がつくことがあります。
これは「元の音符の長さ × 1.5倍」にするという意味です。
例えば「付点2分音符」なら、2拍 × 1.5 = 3拍の長さになります。
音を出さない時間「休符」の種類と長さ
音楽は、音を出す時間と同じくらい「音を出さない時間(休符)」も重要です。
休符にも音符と同じように長さの種類があります。
- 全休符(ぜんきゅうふ):4拍休みます(第4線からぶら下がる四角)。
- 2分休符(にぶきゅうふ):2拍休みます(第3線の上に乗る四角)。
- 4分休符(しぶきゅうふ):1拍休みます(カギのような形の記号)。
- 8分休符(はちぶきゅうふ):0.5拍(半拍)休みます。
これらの音符と休符の長さを組み合わせることで、曲の「リズム」が作られていきます。
これだけは覚えたい!その他の重要な楽譜記号
ドレミの位置と音の長さがわかれば、楽譜の7割は読めたようなものです。
最後に、ピアノ楽譜の読み方で初心者が覚えておきたい、最低限の記号をいくつか紹介します。
拍子記号(ひょうしきごう)
拍子記号とは音部記号の隣に書かれている、分数のような記号です。
例えば「4/4」と書かれていたら、「(下の4)=4分音符を」「(上の4)=1小節に4つ分」入れるリズムですよ、という意味です。
つまり「タン・タン・タン・タン」というリズムが基本になります。
「3/4」(4分の3拍子)なら「タン・タン・タン」で1セットです。
♯(シャープ)と♭(フラット)
音符の左横についている「♯」や「♭」は、音を変化させる記号です。
- ♯(シャープ):その音を「半音上げる」という意味。 ピアノでは、指定された音のすぐ右隣にある黒い鍵盤(黒鍵)を弾きます。
- ♭(フラット):その音を「半音下げる」という意味。 ピアノでは、指定された音のすぐ左隣にある黒い鍵盤(黒鍵)を弾きます。
小節線(しょうせつせん)と複縦線(ふくじゅうせん)
五線譜の途中に引かれている縦の棒を「小節線(しょうせつせん)」といい、楽譜の区切りを示します。
拍子記号で決められた拍数ごとに、この線で区切られており、この区切られた一つのハコを「小節(しょうせつ)」と呼びます。
そして、曲の一番最後に引かれている、細い線と太い線の2本セットを「複縦線(ふくじゅうせん)」または「終止線(しゅうしせん)」といい、曲の終わりを示します。
ピアノ楽譜の読み方【初心者】が挫折しないための練習法
基本的なルールは理解できても、いきなり両手でスラスラ弾くのは難しいものです。
ピアノ楽譜の読み方で初心者が挫折しないためには、練習のステップを細かく分けることが非常に重要です。
1. まずは「音の高さ」だけを読む
最初は、音の長さ(リズム)はすべて無視して、楽譜に書かれている「ドレミ」だけを声に出して読んでみましょう。
ト音記号なら「ド、ミ、ソ、ミ、ド…」のように、まずは音の高さを目で追う練習(譜読み)に集中します。
2. 次に「リズム」だけを手で叩く
音の高さが読めるようになったら、今度は逆に音の高さを無視して、「リズム」だけを手拍子で叩いてみます。
メトロノームなどを使いながら、「タン・タ・タ・ター(休)」のように、音符と休符の長さを正確に体で覚えます。
3. 最後に「片手ずつ」ゆっくり弾いてみる
「音の高さ」と「リズム」を別々に練習したら、最後にそれを組み合わせてピアノで弾いてみます。
この時、いきなり両手で弾こうとせず、必ず「右手だけ(ト音記号)」、次に「左手だけ(ヘ音記号)」と、片手ずつ完璧に弾けるようになるまでゆっくり練習しましょう。
両手がそれぞれスムーズに弾けるようになったら、最後は両手で合わせてみます。
このステップを踏むことが、結果的に一番の近道になります。
まとめ:楽譜は「ルール」がわかれば怖くない!
今回は、ピアノ楽譜の読み方について、初心者の方が最低限知っておくべき基本を解説しました。
- 楽譜は「五線譜」を土台にしている
- 高い音は「ト音記号」(右手)、低い音は「ヘ音記号」(左手)で書かれる
- ピアノの音符の読み方は、「線」と「間」の位置で音の高さ(ドレミ)が決まる
- 音符と休符の形で、音の長さや休む長さが決まる
楽譜は、外国語を学ぶのと少し似ています。
最初は難しく感じるかもしれませんが、基本的な単語(音符)と文法(記号のルール)を一つずつ覚えていけば、必ず読めるようになります。
もし独学での学習が難しいと感じたら、初心者向けの楽譜の読み方ドリルや、解説が丁寧な教本を活用するのも非常に効果的です。
焦らず、ご自身のペースで「音楽の言葉」を学んでいきましょう!