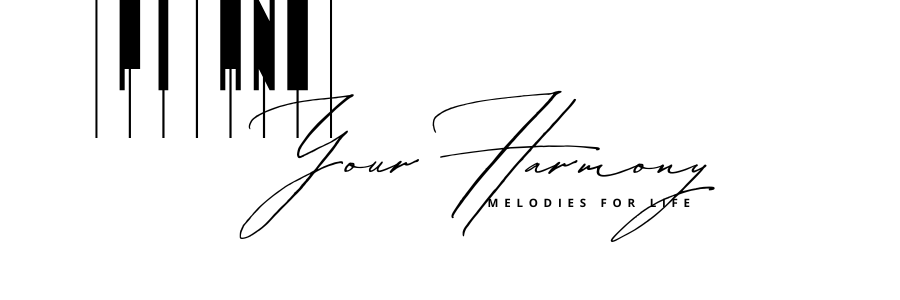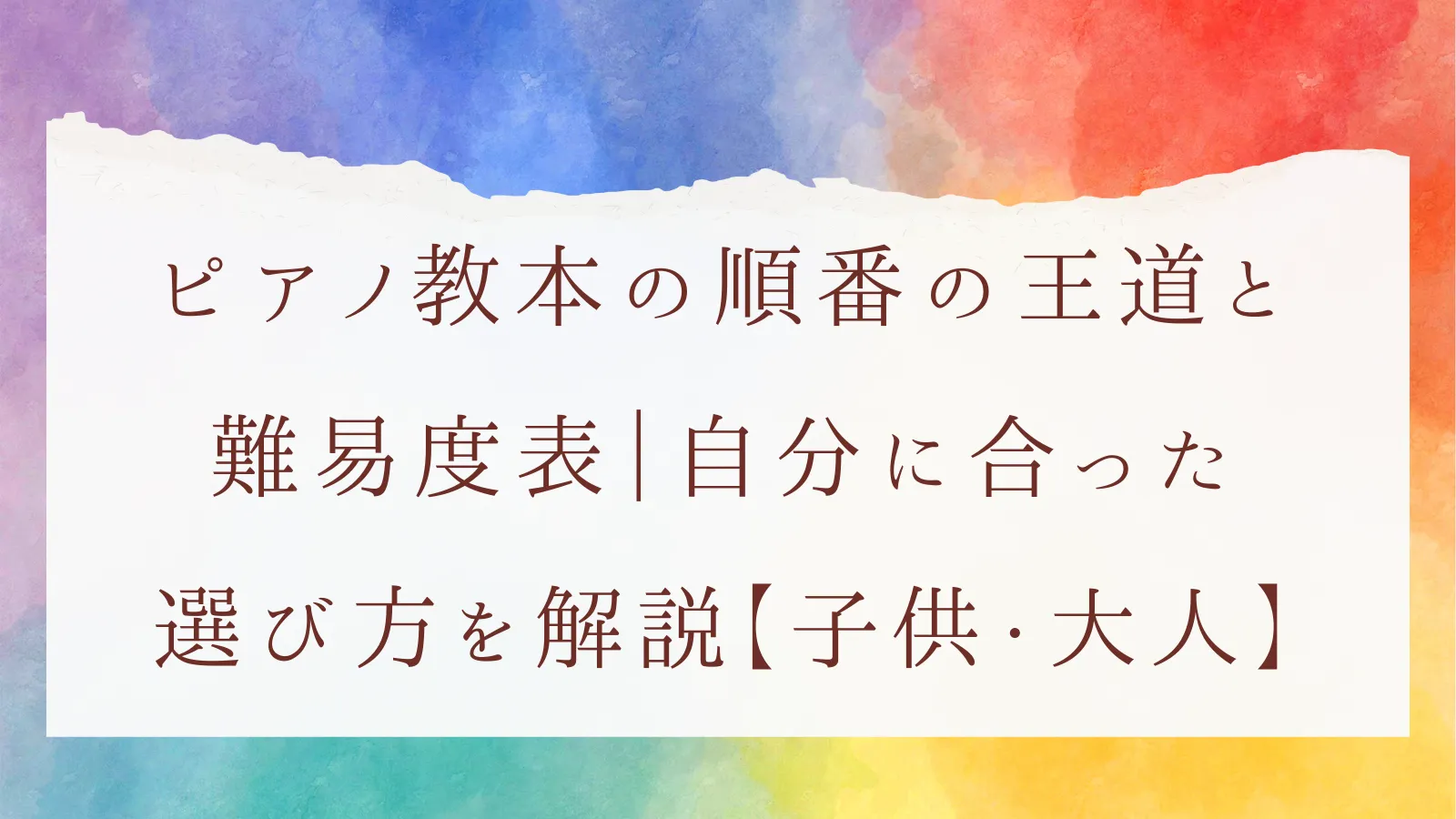ピアノの教本選び、その順番に悩んでいませんか?
「子供のレッスン、どの教本から始めたらいい?」
「大人になってからピアノを再開したいけど、何から手をつければ…」
「バイエルは本当に必要なの?」「ソナチネの次は何に進むべき?」
こういった疑問をおもちの方も多いかもしれません。
はじめに、この記事で紹介するのは、主に日本のピアノ教育で伝統的とされてきた「王道」の進め方です。これはクラシックピアノの技術を体系的に学ぶ上で非常に効果的な道筋ですが、これが唯一の正解というわけではありません。
特に、趣味としてピアノを始めたり、大人になって再開されたりする方にとって、「すべてを完璧に順番通りこなさなくては」という考え方は、かえってピアノを楽しむ心を縛ってしまう可能性もあります。
ピアノの上達には、自分に合った教本を適切な順番で進めることが一つの重要な要素です。しかし、それ以上に大切なのは、あなたがピアノを通じて何を得たいか、という目的そのものです。
この記事では、確立された上達への道筋を示しつつ、あなたがあなた自身の楽しみ方を見つけるための、より柔軟な「ピアノとの付き合い方の地図」を提示します。
こんな方におすすめ
- 子供に合ったピアノ教本の進め方が知りたい
- 大人になってからピアノを始める、または再開する
- 独学でピアノを練習していて、次のステップに迷っている
- 現在使っている教本のレベルや、次に進むべき教本を知りたい
ピアノの教本の順番を知りたいあなたへ:まず押さえるべき基本
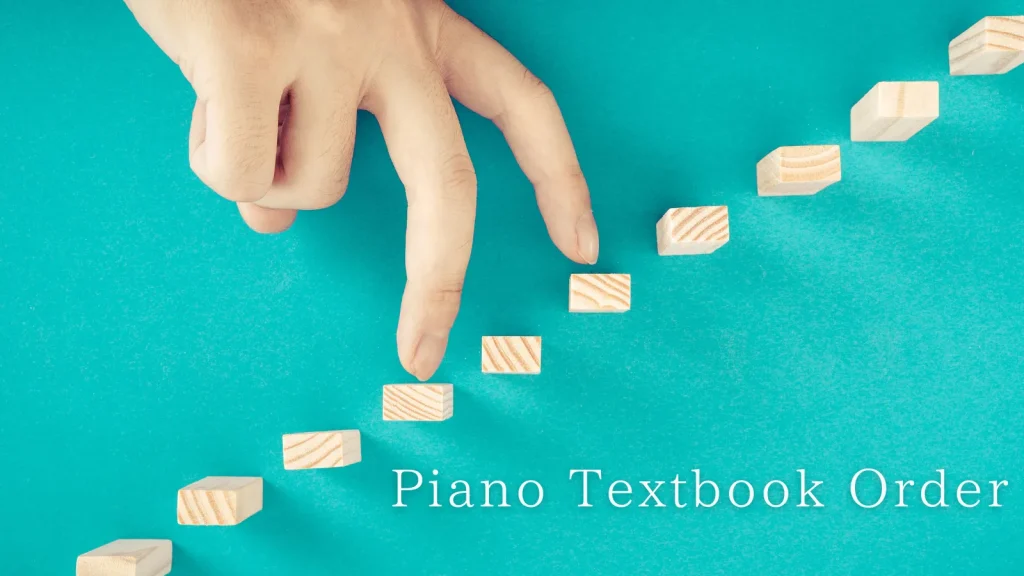
- なぜ教本を進める順番が大切なのか
- 独学とレッスンで進め方は変わる?
- この記事でわかるピアノ教本のレベルと流れ
なぜ教本を進める順番が大切なのか
ピアノの練習を効果的に進める上で、教本をどのような順番で使うかは極めて重要です。その理由は、ピアノの上達が「テクニック」「エチュード」「レパートリー」という、相互に支え合う「三本柱」によって成り立っているからです。
テクニックとは、「ハノン」に代表されるような、指の強さや独立性といった純粋な運動能力を鍛える練習です。エチュードは練習曲とも呼ばれ、「ツェルニー」や「ブルグミュラー」のように、特定の技術を音楽的な文脈の中で習得する目的があります。
そしてレパートリーは、「ソナチネ」などの芸術的な楽曲そのものを指し、技術を統合して音楽を表現する段階です。これらの関係は一方通行であり、前の段階が次の段階の土台となります。例えば、テクニック教本で指の力が養われていなければ、エチュードの速いフレーズは弾けません。
そして、エチュードで技術的なパターンを習得していなければ、レパートリーを音楽的に表現することは困難です。
このように、教本を体系的に進めることは、理想的な上達への道筋を築くことにつながるのです。しかし、この道筋が絶対的なものではないということも、心に留めておくと良いでしょう。
独学とレッスンで進め方は変わる?
独学かレッスンかによって、ピアノ教本の進め方は変わってきます。独学の場合、非常に体系的で少しずつ難易度が上がる「バイエル」のような教本は、一人でも進めやすいという利点があります。
しかし、モチベーションの維持が大きな課題となるため、自分の弾きたい曲に挑戦したり、達成可能な短期目標を設定したりといった工夫をするのがおすすめです。
一方、レッスンでは先生という指導者がつきます。指導者は、学習者の目標や性格に合わせて、数ある教本の中から最適なものを組み合わせたり、一つの教本の中でも特に重要な曲を抜粋してくれたりします。
これにより、練習を効率化し、個々に最適化された「オーダーメイドの道筋」を設計することが可能です。独学でも上達は可能ですが、レッスンを受けることで、よりスムーズでバランスの取れた学習が期待できるでしょう。
この記事でわかるピアノ教本のレベルと流れ
ピアノの学習過程は、全体像を把握するために、一般的に「導入」「初級」「中級」「上級」という4つの段階に分けて考えることができます。
この記事では、この普遍的な4段階モデルを基準に、ピアノ教本の流れを解説していきます。
導入は、ピアノに初めて触れ、楽譜の読み方の基本を学ぶ段階です。初級では、両手を使った簡単な演奏が可能になり、「バイエル」の修了が一つの目安とされます。
中級に進むと、「ソナチネ」のようなより複雑な楽曲に取り組み、表現力が求められ始めます。そして上級では、本格的な演奏会用のレパートリーに挑戦する高度なレベルへと至ります。
この4段階のフレームワークを理解することは、あなたが今どこにいるのかという現在地を把握し、次にどこへ向かうべきかという目標を設定するための、信頼できる地図となるでしょう。
レベル別で見るピアノ教本の一般的な順番と難易度マップ

- 初級:バイエルから始める王道の進め方
- 中級:ブルグミュラーからソナチネへの道
- 上級:ソナチネの次とその先の教本たち
- ピアノ教本全体の難易度レベル表(目安・参考)
初級:バイエルから始める王道の進め方
日本のピアノ教育には、長年確立されてきた「王道」と呼ばれる伝統的なカリキュラムが存在します。
その出発点となるのが、フェルディナンド・バイエルによって作られた「バイエル」です。この教本は、単旋律から始まって徐々に両手奏へと進む非常に段階的な構成で、クラシック音楽の基礎を着実に築くことができます。
バイエルを終えた学習者が次に手に取るのが、ヨハン・ブルグミュラーによる「ブルグミュラー25の練習曲」です。この教本は、「素直な心」や「アラベスク」といった美しい題名が付けられた曲で構成されており、技術練習だけでなく、音楽的な表現力を養うことを目的としています。
バイエルで培った基礎の上に、ブルグミュラーで音楽性を加える、これが日本の伝統的な初級カリキュラムの進め方です。
中級:ブルグミュラーからソナチネへの道
ブルグミュラーで音楽表現の楽しさを学んだ後、学習者は中級レベルへとステップアップします。ここでの中心となるのが、ベートーヴェンの弟子であったカール・ツェルニーによる練習曲と「ソナチネアルバム」です。
「ツェルニー30番練習曲」は、指の速さや均一性を鍛えることに特化したエチュードであり、より高度な技術を体系的に習得するために使われます。
そして、この技術を使って挑戦するのが、クレメンティやクーラウなどが作曲した「小さなソナタ」を集めた「ソナチネアルバム」です。
これは、本格的なクラシック作品の構造を理解するための重要なレパートリー教本となります。技術を磨くツェルニーと、それを応用して芸術性を高めるソナチネを並行して進めるのが、中級の標準的な学習ルートです。
上級:ソナチネの次とその先の教本たち
中級の核心であるソナチネアルバムを終えると、いよいよ上級レベルへの扉が開かれます。ここからは、より本格的で芸術性の高いレパートリーに取り組んでいくことになります。
ソナチネの次に進む道筋として一般的なのは「ソナタアルバム」です。これには、モーツァルトやベートーヴェンといった偉大な作曲家による、より規模が大きく複雑なソナタが収められています。
技術面では、「ツェルニー30番」に続いて「ツェルニー40番」や「50番」へと進み、さらに高度な指の訓練を続けます。
また、複数のメロディを同時に弾き分ける能力を養うために、バッハの「インヴェンションとシンフォニア」なども重要な教本となります。
最終的には、ショパンのエチュードのような、技術的にも音楽的にも最高峰の作品が目標として視野に入ってきます。
ピアノ教本全体の難易度レベル表(目安・参考)
| レベル | メイン教本(メソード) | テクニック教本 | エチュード(練習曲) | レパートリー(楽曲) |
| 導入 | ぴあのどりーむ 1-2 オルガン・ピアノの本 1-2 |
バーナム 導入書 | はじめてのギロック | - |
| 初級 I | バイエル 上巻 ぴあのどりーむ 3-4 オルガン・ピアノの本 3 |
バーナム 1 | こどものツェルニー ギロック 叙情小曲集(抜粋) |
- |
| 初級 II | バイエル 下巻 ぴあのどりーむ 5-6 オルガン・ピアノの本 4 |
ハノン (導入) バーナム 2 |
ブルグミュラー 25の練習曲 ツェルニー 100番 |
プレ・インヴェンション |
| 中級 I | (メイン教本から卒業) | ハノン バーナム 3 |
ツェルニー 30番練習曲 ブルグミュラー 18の練習曲 |
ソナチネアルバム 1 バッハ インヴェンション |
| 中級 II | (メイン教本から卒業) | ハノン バーナム 4 |
ツェルニー 40番練習曲 | ソナチネアルバム 2 バッハ シンフォニア |
| 上級 | (メイン教本から卒業) | ハノン | ツェルニー 50番練習曲 ショパン エチュード |
ソナタアルバム バッハ 平均律クラヴィーア曲集 |
【子供・大人別】おすすめのピアノ教本と進める順番
- 子供・小学生におすすめの教本の順番と特徴
- 大人からピアノを始める場合の教本の選び方と順番
- なぜ子供と大人で使う教本や順番が違うのか
子供・小学生におすすめの教本の順番と特徴

子供、特に幼児や小学生がピアノを始める場合、楽しさを最優先し、音楽とポジティブな関係を築くことが何よりも大切です。そのため、現在は伝統的な「バイエル」ではなく、現代的なアプローチの教本から始めるのが一般的です。
幼児(3歳~7歳頃)には、田丸信明さんが作曲した「ぴあのどりーむ」が最適です。美しいカラーイラストと歌える歌詞が特徴で、非常にゆっくりとしたペースで進むため、子供が挫折することなく学べます。
これに、身体の動きとテクニックを結びつけて楽しく学べる「バーナム ピアノテクニック ミニブック」を組み合わせるのがおすすめです。小学生(8歳~12歳)になると、より体系的な学習も可能になりますが、やはり魅力的な教材が効果的です。
「ぴあのどりーむ」から始めることもできますし、アメリカの「バスティン」や「トンプソン」といった、理論や多様なスタイルを統合的に学べるメソードも良い選択肢です。
そして、「ぴあのどりーむ」の4巻あたりや「バイエル」を終えた段階で、「ブルグミュラー25の練習曲」に進むのが自然な流れとなります。
大人からピアノを始める場合の教本の選び方と順番

大人がピアノを始める場合、その目標によって最適な教本の順番は大きく変わります。クラシック志向の方でも、「体系的に基礎から学びたい」のか、「とにかく憧れのあの曲が弾きたい」のかでアプローチは異なります。
体系的に学びたい方には、効率性とモチベーションの維持が鍵となります。「おとなのためのバイエル」や、親しみやすい名曲とテクニックを組み合わせた大人向けの教本から始め、指の練習に「ハノン」を併用するのが良いでしょう。その後は、「ブルグミュラー」「ツェルニー30番」「ソナチネ」へと進みます。
一方、趣味として楽しみ、弾きたい曲が明確にある場合は、その曲を弾き上げることが最終目標です。その過程はもっと自由で構いません。例えば、弾きたい曲の中で出てくる技術に絞って、ハノンや練習曲集の中から必要な部分だけを抜き出して練習するのも一つの方法です。
極端に言えば、練習曲集は使わず、弾きたい曲の中の難しい箇所だけを徹底的に練習したって良いのです。「~しなければならない」という考えから自由になれば、ピアノはもっと楽しくなります。

なぜ子供と大人で使う教本や順番が違うのか

子供と大人でピアノ教本の順番や選び方が異なるのは、学習における優先順位や目的が根本的に違うからです。子供は楽しさを、大人は目標達成への効率性を重視する傾向があります。
しかし、年齢にかかわらず、もう一つとても大切な視点があります。それは、学習者本人と教材との「相性」や「好み」です。
例えば同じ初級レベルであっても、イラストが美しいもの、知っている曲がたくさん入っているもの、シンプルな課題が続くものなど、教本には様々な個性があります。
もし提示された教本が苦痛で、練習が嫌いになり、ピアノから心が離れてしまうくらいなら、それは本人にとって良い教材とは言えません。
ピアノの先生とよく相談しながら、本人が「これなら頑張れそう」と前向きに思える教材や曲を選ぶこと。それが、結果的にピアノを長く楽しむための最も良い選択となるはずです。

ピアノ教本の順番でよくある疑問を解決
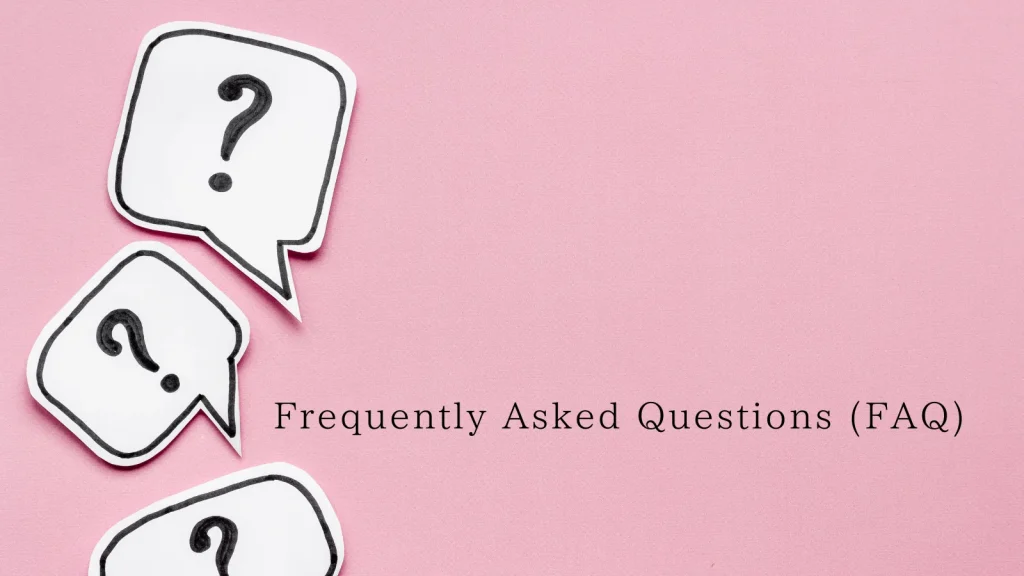
Q1. 教本は順番通りに進めないとダメ?目標別の考え方
Q2. 複数の教本を併用するメリットとおすすめの組み合わせは?
Q3. 自分のレベルに合った教本がわからない時の対処法は?
さいごに:教本の順番に迷ったら先生に相談するのが一番
Q1. 教本は順番通りに進めないとダメ?目標別の考え方
教本を順番通りに進めるべきか、あるいは飛ばしても良いのか。この問いに対する答えは、あなたがピアノを学ぶ目標によって大きく異なります。
【趣味として楽しみたい場合】
もしあなたが趣味としてピアノを楽しみたいのであれば、答えは「必ずしも順番通りでなくても良い」です。例えば、「バイエル」は現代の子供の導入教材としては必須ではなく、より魅力的な代替教材で始めるという選択も十分に考えられます。
実際、アマチュアとしてピアノを楽しむ多くの人が、すべての教材を完璧に終えているわけではありません。練習曲は苦手でも、弾きたい憧れの曲に集中して練習することで、コンクールでソナタレベルの曲を弾き、上位入賞を果たしたという経験を持つ方もいます。
これは、ツェルニーを途中でやめたり、ハノンのスケールを全部は終えていなくても、目標の曲に必要な技術を集中して磨いた結果です。基礎練習はもちろん重要ですが、それ自体が目的になってピアノが楽しくなくなっては本末転倒。あなたにとってのゴールを見失わないことが何よりも大切です。
【音大やプロを目指す場合】
一方、ピアニストや音大進学といった専門家の道を目指すのであれば、話は異なります。この場合は、教本を順番通りに、そして抜けなく取り組むことが非常に重要になるでしょう。
プロに求められるのは、特定の曲が見事に弾けること以上に、どんな時代のどんな楽曲にも対応できる、盤石で安定したテクニックの土台です。
ツェルニーの練習曲やバッハのインヴェンションといった基礎的な練習を自己判断で飛ばしてしまうと、それが将来、特定の指の動きや音楽的解釈における技術的な「穴」となり、より高度な曲を演奏する上での大きな壁になりかねません。
そのため、プロを目指す道においては、一つひとつの教本が次のステップに進むための重要な投資です。地道に、そして着実に全ての課題をクリアしていく、徹底した取り組みが不可欠と言えるでしょう。
Q2. 複数の教本を併用するメリットとおすすめの組み合わせは?
複数の教本を併用することには、ピアノをバランス良く上達させるための大きなメリットがあります。これは、ピアノ学習が「テクニック(指の練習)」「エチュード(練習曲)」「レパートリー(楽曲)」という三つの異なる目的を持つ練習の組み合わせで成り立っているからです。
一つの教本だけでは、これらの要素をすべてカバーすることはできません。効果的な組み合わせの例として、初級後半から中級初期にかけては、「ブルグミュラー25の練習曲」で音楽性を養い、「ツェルニー100番」で技術を補強し、日々のウォームアップとして「ハノン」を取り入れる、というものが挙げられます。
中級レベルでは、「ソナチネアルバム」というレパートリーに、「ツェルニー30番」というエチュード、そしてバッハの「プレ・インヴェンション」で多声音楽の訓練を加える、といった組み合わせが理想的です。
このように、目的の異なる教本を組み合わせることで、各教材が互いを補い合い、総合的なピアノの力を効率的に伸ばすことができるのです。
Q3. 自分のレベルに合った教本がわからない時の対処法
自分のレベルに合った教本がわからなくなってしまった時は、まずピアノ学習の全体像における自分の現在地を確認することが大切です。学習段階は大きく「導入」「初級」「中級」「上級」に分けられます。
例えば、「バイエル」を終えた段階なら初級修了レベル、「ブルグミュラー」を練習中なら中級への移行期、というように、自分がどのステージにいるのかを把握しましょう。
次に、検討している教本の目的を理解することが重要です。指のトレーニングをしたいのか、音楽的な表現力を高めたいのか、あるいはクラシックの楽曲形式を学びたいのかによって、選ぶべき教本は変わります。
そして最後に、自分の直感や「好み」を大切にすることも忘れずに。練習を続けるのは他の誰でもなく、あなた自身です。
愛着を持って取り組める一冊を選ぶことが、上達への隠れた近道になることもあります。
さいごに:教本の順番に迷ったら先生に相談するのが一番

独学で進めることも可能ですが、ピアノ教本の順番に本当に迷ってしまった時は、ピアノの先生に相談するのが最も確実で効果的な解決策です。
独学では、数えきれないほどの教本の中から自分に最適な一冊や、効果的な組み合わせを見つけ出すのは非常に困難です。
ピアノの先生は、長年の経験と専門知識に基づき、あなたの現在のレベル、目標、性格、そして教材との相性まで考慮して、最適な学習プランを立ててくれます。
例えば、モチベーションを維持するために、基礎的な練習と並行してあなたの弾きたい曲を取り入れたり、分厚い教本の中から本当に必要な曲だけを効率よく抜粋してくれたりします。
自分一人で地図もなく広大な森をさまようのではなく、経験豊富なガイドに案内してもらうように、先生に相談することが、上達への一番の近道と言えるでしょう。
ポイント
- ピアノ上達の基本はテクニック、エチュード、レパートリーの三本柱
- 教本の順番はこの三本柱を育てるための効果的な道筋の一つ
- 王道の進め方は絶対ではなく、あくまで日本の標準的な一例
- 子供の学習は楽しさを、大人は目標達成を重視する傾向がある
- 年齢を問わず、教材との相性や好みも非常に大切な要素
- 憧れの曲から必要な技術だけを抜き出して練習するのも有効な手段
- 教本をすべて完璧に終えなくても高いレベルの演奏は可能
- 複数の教本を併用すると総合的なピアノの力を伸ばしやすい
- ソナチネアルバムは難易度順ではないため順番に注意が必要
- 迷ったら個々の目標や相性も見てくれる先生に相談するのが最善
番外編:アプリでピアノを始めるという選択肢
以下の記事で、人気のアプリについて詳しくレビューしています。ぜひ参考にしてくださいね。