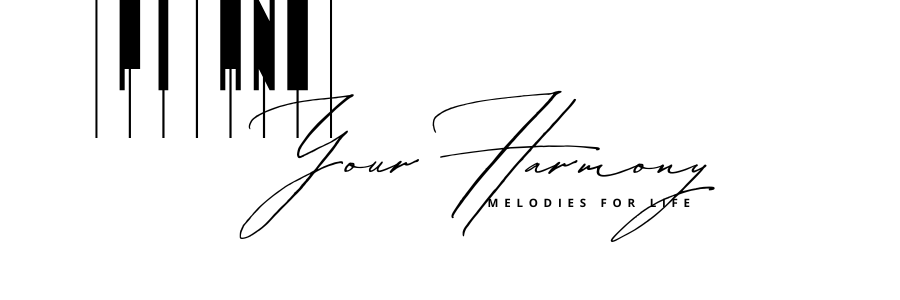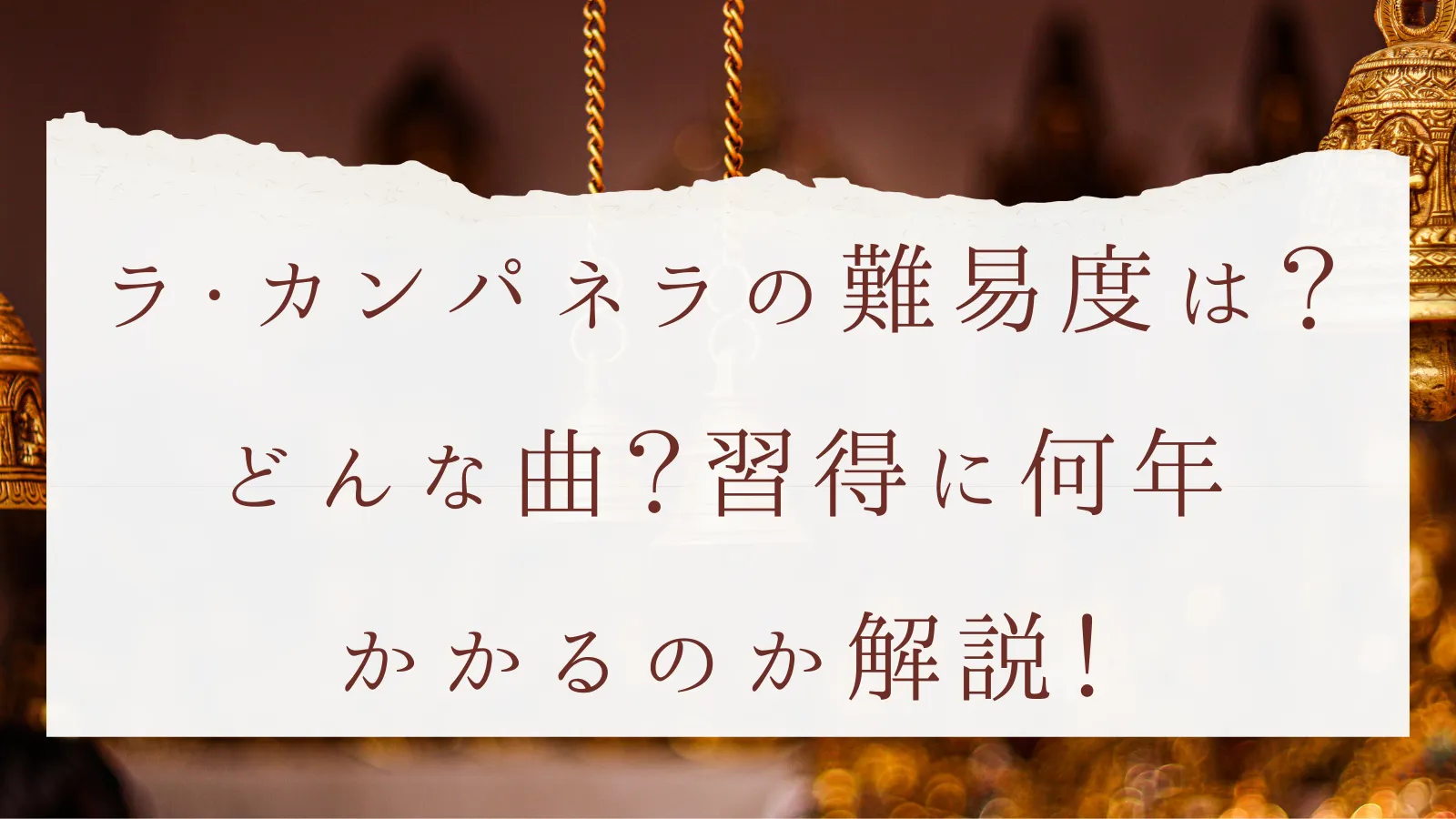フランツ・リストの作曲した「ラ・カンパネラ」。その輝かしく美しい鐘の音は、多くのピアノ学習者にとって永遠の憧れです。しかし、その一方で「超絶技巧曲」として知られ、その難易度の高さは数々のピアニストを悩ませてきました。
インターネットの知恵袋などを見ると「全音の楽譜では難易度E(上級)だけど、本当にそのレベル?」「英雄ポロネーズとラ・カンパネラはどっちが難しいの?」といった疑問も寄せられています。
また、「一体何年練習すれば弾けるようになるのか」「そもそも弾ける人数はどれくらいいるのか」といった、習得までの道のりに関する声も聞かれます。
この記事では、そんな「ラ・カンパネラ」の難易度について、国内外の客観的な評価基準を紹介しつつも、それが全てではないという視点から、具体的な難しい理由、他の名曲との比較、そして習得に必要な道のりまで、あらゆる角度から解説していきます。
こんな方におすすめ
- ラ・カンパネラの難易度の目安を客観的な指標から知りたい
- 難しいといわれる理由を知りたい
- いつか挑戦したいけれど、何から始めればいいか分からない
- 英雄ポロネーズなど他の難曲との違いを知りたい
ラ・カンパネラの難易度は?客観的な指標から解説
この項の概要
結論:ピアノ曲の中でも最難関クラスの超絶技巧曲
結論から言うと、リストの「ラ・カンパネラ」は、ピアノのレパートリー全体の中でも「最難関クラス」に位置する超絶技巧曲です。
その技術的な要求は極めて高く、プロのピアニストでさえも演奏会で取り上げるには入念な準備を必要とします。単に「上級者向け」という言葉では表現しきれない、特別なレベルの楽曲であると断言できます。
全音ピアノピースの難易度「E」は本当?知恵袋でも話題の謎
ピアノ学習者に広く親しまれている全音楽譜出版社の「全音ピアノピース」シリーズでは、リスト作曲「ラ・カンパネラ」が「E:上級」に分類されています。これは、同じくEランクであるリストの「愛の夢 第3番」やショパンの「幻想即興曲」と、同程度の難易度であることを示しています。
しかしながら、この評価に疑問を抱く声も少なくありません。実際、「ラ・カンパネラ」はこれらの曲と比べても格段に高度な技巧を要求し、むしろ上位ランクである「F:上級上」に分類されているショパンの「革命のエチュード」よりも難しいと感じる演奏者もいるほどです。
では、なぜこのような評価のズレが生じるのでしょうか。
その背景には、全音による難易度評価が、単に演奏技術の難しさだけでなく、以下のような複数の要素をもとに総合的に判断されている可能性があります:
-
楽曲の知名度や親しみやすさ
-
楽譜の視覚的な複雑さ
-
曲の長さや構成
-
一般的な演奏頻度や受容度
「ラ・カンパネラ」は比較的短く、主題が明確で、同じモチーフが繰り返される構成を持っています。そのため、譜面上では一見、難易度が抑えられているように見えるかもしれません。しかし実際には、極端な跳躍や超絶技巧を要するパッセージが随所に現れ、プロの演奏家にとっても非常に手強い楽曲であることに変わりはありません。
そのため、「E」というランク付けはカタログ上の分類としては妥当であるものの、実際の演奏難易度を十分に反映しているとは言い難いという見方も存在します。
ピティナや海外の評価は?客観的な難易度指標
一方で、演奏技術そのものを厳密に評価する専門的な基準を見ると、「ラ・カンパネラ」の位置づけがより明らかになります。
全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)の評価では、同曲は最高難易度帯である「展開1, 2, 3」や、コンペティションの最上級部門「F級」に指定されています。これは、演奏家レベルの極めて高度な技術が要求されることを意味しており、現場のピアニストが体感する難易度と一致します。
国際的な基準に目を向けても同様です。英国王立音楽検定(ABRSM)やトリニティ・カレッジ・ロンドンのような権威ある機関では、この曲は一般的なグレード試験(1〜8級)をはるかに超えた、プロレベルの演奏家資格(ディプロマ)の課題曲として扱われています。
ただし、ここで強調しておきたいのは、これらの評価はあくまで客観的な「指標の一つ」に過ぎないということです。人によって手の大きさや骨格、得意な技術や苦手な技術は全く異なります。
ある人にとっては楽に感じるパッセージが、別の人にとっては最大の難所になることも珍しくありません。これらの指標は自分の現在地を知るための有効なツールですが、それが難易度の全てではないということを心に留めておくことが大切です。
ラ・カンパネラが絶望的に難しい3つの理由
この項の概要
理由1:過酷なまでの「跳躍」- 鍵盤を見ずに弾く超絶技巧
「ラ・カンパネラ」の難易度を象徴するのが、曲全体を通して執拗に繰り返される右手の「跳躍」です。その距離は1オクターブ(15度)を超えることが当たり前で、時には2オクターブ以上(16度)も離れた鍵盤へ、16分音符という一瞬の時間で手を移動させなければなりません。
この跳躍は非常に目立つため、わずかなミスタッチも許されず、完璧な正確性が求められます。これを実現するには、指先の力だけでなく、手首や腕の力を抜き、体全体を使ってしなやかに手を目標地点へ導く高度な身体操作が必要です。
鍵盤を見ずとも距離感を正確に把握する「鍵盤感覚(固有受容性感覚)」を、何千回もの反復練習によって身体に染み込ませる必要があります。
この訓練を怠り、力任せに音を叩こうとすると、腕や手首に過剰な負担がかかり、腱鞘炎といった深刻な怪我につながるリスクが非常に高くなります。独学者が挫折しやすい最大の理由がここにあります。
理由2:弱い指の高速トリルと同音連打- 指の独立性が試される
この曲の挑戦は跳躍だけではありません。ピアニストの指の能力を極限まで試す、多彩な技巧が散りばめられています。
特に悪名高いのが、薬指(4の指)と小指(5の指)という、構造的に最もコントロールが難しい指で演奏される高速のトリルです。これらの指を独立させて均一な音を鳴らすには、指の力だけでなく、前腕の回転運動を巧みに利用する高度なテクニックが不可欠です。
さらに、楽曲の後半には同じ音を高速で連打するパッセージや、きらびやかな半音階も登場します。これらの技巧はすべて、各指が他の指に影響されずに独立して動く「指の独立性」がなければ演奏不可能です。
一つの手で主旋律を歌わせながら、同時に鐘の音を模した装飾音を軽やかに奏でるという、まさに神業が求められるのです。
理由3:技術を超えた音楽表現 - 鐘の音を美しく響かせる難しさ
「ラ・カンパネラ」の最終的なゴールは、技術的な難所をすべてクリアすることではありません。その難しさを聴衆に一切感じさせず、まるで本物の鐘のように、どこまでも軽やかで美しい音色を響かせることにあります。
リストは楽譜に「弱く、しかし常に主題はよく目立つように」と書き込んでいます。これは、きらめく高音の装飾音を繊細にコントロールしつつ、主旋律だけをクリアに浮かび上がらせる、極めて高度な音量調節(ヴォイシング)技術を要求するものです。
また、鐘の響きを生み出すペダルの使い方も非常に繊細です。踏みすぎれば音が濁ってしまい、楽曲本来の輝きが失われます。そのため、打鍵した「後」に踏み、次の音を弾く「瞬間」に離すといった、コンマ数秒単位での繊細なペダル操作が不可欠です。
そもそも何をもって「難しい」とするかの定義自体が非常に困難ですが、技術的に完璧に音を並べることができても、音楽的な美しさを追求する旅には終わりがありません。この芸術性の追求こそが、この曲の最も深く、尽きることのない挑戦と言えるでしょう。
ラ・カンパネラは他の曲と比べてどれくらい難しい?
この項の概要
英雄ポロネーズとどっちが難しい?難しさの質を徹底比較
ピアノを学ぶ人なら一度は気になる、「ラ・カンパネラ」とショパン作曲「英雄ポロネーズ」の難易度比較。しかし、この2曲で求められる技術や表現力はまったく異なるため、単純に「どちらが難しい」と結論づけることはできません。
「ラ・カンパネラ」の難しさは、超高速の大きな跳躍や、弱い指でのトリルなど、精密で繊細な動きが求められる点にあります。一方、「英雄ポロネーズ」では、特に中間部の左手による執拗なオクターブ連打のように、純粋な体力や持久力、そして全体を力強くまとめ上げる音楽的な構成力が求められます。
このように、両曲が求めるスキルはまったく異なるため、「どちらが難しいか」を単純に比べることはできません。精密な動きに強い人もいれば、スタミナと表現力で勝負するタイプもいます。
だからこそ、この比較は“どちらが上か”を決めるためではなく、それぞれの曲が持つ独特の難しさやチャレンジの方向性――いわば「難しさの質」を理解することに意味があるのです。
世界最難関ではない?ピアノ曲難易度ランキングでの位置づけ
「ラ・カンパネラ」は、しばしば「世界で最も難しいピアノ曲」といったリストに登場します。その理由は、ピアニストの手が鍵盤上を激しく飛び交う様子が非常に視覚的で、誰の目にもその難しさが分かりやすいからです。
しかし、専門家の間では、この曲はピアノレパートリーの「絶対的な最難関」とは見なされていません。そして、そもそもピアノ曲の難易度ランキングというもの自体が、絶対的なものではないと理解しておく必要があります。
最難関候補として挙げられるラヴェルの「夜のガスパール」やリスト自身の「鬼火」なども、それぞれ異なる種類の困難さを内包しています。
原曲のヴァイオリンはもっと難しい?パガニーニとの関係
「ラ・カンパネラ」の主題は、もともとイタリアの伝説的なヴァイオリニスト、ニコロ・パガニーニが作曲したヴァイオリン協奏曲の最終楽章から取られています。若き日のリストは、ニコロ・パガニーニの常軌を逸した演奏に衝撃を受け、「私はピアノのパガニーニになる」と決意しました。
この曲は、単なる編曲ではありません。ヴァイオリンの特殊な演奏技法(フラジオレットやスピッカート)によって生み出される鐘の効果を、ピアノという全く異なる楽器の語法で「再創造」しようとした、リストの野心的な挑戦の産物です。
ヴァイオリンの原曲ももちろん超絶技巧を要しますが、リストはその技巧をピアノで再現し、時には凌駕しようとしました。その結果として、「ラ・カンパネラ」の難易度は必然的に前人未到の領域へと引き上げられたのです。
ラ・カンパネラ習得への道|何年かかる?どんな練習が必要?
この項の概要
弾けるようになるまで何年かかる?期間の目安と必要な練習時間
「ラ・カンパネラを弾けるようになるまで何年かかりますか?」という質問への答えは、学習者の経歴や練習量、そして「弾ける」の定義によって大きく異なります。
ある漁師が、毎日5時間から8時間というプロ顔負けの練習を「ラ・カンパネラ」一曲のために続け、約7年かけて人前で演奏できるレベルに到達したという話があります。
50歳を過ぎてから独学でピアノを始めた徳永義昭さんは、過酷な漁の合間を縫ってピアノに向かい続け、ついには映画のモデルにもなるほど注目を集めるようになりました。音符の読み方から手探りで始めた練習は、やがて1日10時間近くに及ぶこともあり、途中でやめたいと思ったことは一度もなかったそうです。
しかし、一般的な音楽教育の基準で言えば、「ラ・カンパネラ」は音楽大学に入学した後、あるいはそれ以上のレベルで取り組むべきレパートリーです。これは、体系的なピアノの訓練を10年から15年以上積んだ後に、ようやく到達できるレベルであることを示唆しています。
大切なのは、「音を並べること」と「音楽を奏でること」は違うということです。数年で音を弾けるようにはなるかもしれませんが、この曲の芸術性を表現できるレベルに達するには、長年にわたる総合的な音楽家としての成熟が必要不可欠です。
どれだけ周りに無理だと言われても「弾きたい」という気持ちが、徳永さんを毎日ピアノに向かわせる原動力になったのでしょう。ラ・カンパネラを弾けるようになるには、まず「どうしても弾きたい」という情熱が、何より大切なのかもしれませんね。
挑戦に必要な前提条件は?どんなレベルの人が弾けるのか
「ラ・カンパネラ」に挑戦するには、強固な技術的基盤が絶対に必要です。例えばショパンの「幻想即興曲」レベルからいきなりこの曲に挑戦するのは、一般的に推奨されません。無理な挑戦は、悪い癖を定着させたり、怪我をしたりするリスクを高めます。
最低限の前提条件として、以下のようなレベルが目安となります。
- 基礎技術: すべての調の音階やアルペジオを高速かつ均一に弾ける。チェルニー50番、60番レベルを修了している。
- 練習曲: ショパンのエチュード(「革命」「木枯らし」「黒鍵」など)を複数曲マスターしている。
- レパートリー: ベートーヴェンのピアノソナタ(「悲愴」「熱情」など)や、バッハの「平均律クラヴィーア曲集」のフーガを学習し、大規模で多声的な楽曲を構築する能力を養っている。
これらの準備ができて初めて、「ラ・カンパネラ」への挑戦権が得られると考えるべきでしょう。
どの楽譜を選べばいい?原典版・校訂版・簡易版の違い
「ラ・カンパネラ」を練習するにあたり、どの楽譜を選ぶかも重要なポイントです。市場には大きく分けて3種類の楽譜があります。
- 原典版(Urtext): 作曲家の意図を最も忠実に再現した楽譜です。編集者の解釈が加えられていないため、自分で音楽を構築する力が求められますが、最も信頼性が高い選択肢です。
- 校訂版(Edited Edition): 著名なピアニストが運指やペダリングなどの演奏上のアドバイスを書き加えた楽譜です。フェルッチョ・ブゾーニによる版などが有名で、学習の助けになりますが、あくまで校訂者個人の解釈であることを理解する必要があります。
- 簡易編曲版(Simplified): 原曲の難易度を大幅に下げて、学習者が楽しめるように編曲された楽譜です。技術的にまだ原曲に挑戦できない場合に有用ですが、これは芸術作品としての「ラ・カンパネラ」とは全く別のものと認識しておくべきです。
自分のレベルと目的に合わせて、最適な楽譜を選ぶことが上達への近道となります。
まとめ:ラ・カンパネラは憧れに値する最高峰のピアノ曲
ポイント